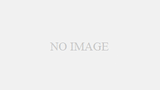闇夜に響く、うなるような風の音。人通りの途絶えた街道に、不気味なほど大きな影が二つ、ゆらめいていた。一人は、いかにも悪の権化といった風貌の男。漆黒の羽織に身を包み、鋭い眼光をぎらつかせている。この地の悪代官、黒沼玄蕃である。もう一人は、玄蕃の傍らでへらへらと愛想笑いを浮かべる小男。呉服商「越後屋」の主、越後屋宗右衛門だ。
「越後屋、今宵もまた、月がこうも丸いとなると、わしの悪事を覆い隠すかのようだ」
玄蕃がにやりと笑うと、越後屋は恐縮したように頭を下げた。
「ははあ、お代官様のお言葉、まことにその通りでございます。この月も、お代官様の御威光にひれ伏しているかのよう」
越後屋の露骨な阿りに、玄蕃は鼻で笑った。
「そちは相変わらず、口がうまいな。さて、越後屋。最近、妙な話を聞くのだ。なんでも、『あおり運転』とやらで、罪もない者が苦しめられているとな」
玄蕃は興味深そうに眉をひそめた。越後屋は心得たりとばかりに、膝を乗り出した。
「ははあ、あおり運転でございますか。それがしめ、現代の世のしきたりには疎いもので、いまいちピンとこぬのですが…」
「ふむ、そなたもか。わしも、詳しいことは分からぬゆえ、そなたに尋ねておるのだ。なんでも、車とやらを操る際、後ろからわざと威嚇したり、急ブレーキをかけたりして、前の者を困らせるのだとか。中には、道を塞いだり、降りてきて因縁をつけたりする者までいるという」
玄蕃は腕を組み、深く考え込んだ。悪事の限りを尽くしてきた玄蕃だが、どこか納得いかない表情を浮かべている。
「なんとも、理解しがたい行為だな。わざわざ危険を冒してまで、他者を困らせて何が楽しいのだ?」
越後屋は玄蕃の問いに、困惑した顔で答えた。
「お代官様のおっしゃる通りでございます。それがしも、その点については首を傾げております。我らが悪事を働くのは、己の腹を満たし、権力を手に入れるため。言わば、目的があるからこそ、手段を選ぶのでございます」
玄蕃は頷き、越後屋の言葉を促した。
「うむ、その通りだ。わしとて、無意味な悪事は好まぬ。銭を手に入れるため、あるいは、わしの権威を示すためならば、多少の非道も辞さないが、今回の『あおり運転』とやらは、どうにも理解に苦しむ」
越後屋は、恐る恐る口を開いた。
「お代官様、それがしなりに、少しばかり調べてみたのでございますが…どうやら、その『あおり運転』とやらを行う者は、己の鬱憤を晴らしたい、あるいは、優位に立ちたいという気持ちが強いようでございます」
「鬱憤を晴らす? 優位に立つ?」
玄蕃は、越後屋の言葉を反芻するように繰り返した。
「そうでございます。日頃の不満やストレスが溜まりに溜まって、それを誰かにぶつけたい。あるいは、普段は誰かに頭を下げるばかりで、なかなか自分の意見が通らない者が、車の運転中だけは自分が一番だと錯覚し、弱い者を見つけては威嚇することで、優越感に浸りたいのだとか」
越後屋は、まるで遠い異国の風習を語るように、淡々と説明した。玄蕃は、しばらく黙って空を見上げていたが、やがて冷笑を浮かべた。
「ふん、なんと愚かなことか。鬱憤を晴らしたいのならば、もっと建設的な方法があるだろうに。権力を欲するのならば、わしのように地位を築けばよい。己の感情のままに他者を傷つけるなど、下衆の所業にも劣るわ」
玄蕃の言葉には、どこか呆れと軽蔑の念が込められていた。越後屋は、すかさず玄蕃の言葉に同意した。
「ははあ、お代官様のおっしゃる通りでございます。まったく、器の小さいことでございます。それに、お代官様は、悪事を働くにも、そこには筋が通っております。弱きをくじき、強きを助ける…いえ、強き者から銭を巻き上げ、弱き者から…」
越後屋が言葉に詰まると、玄蕃は鋭い眼光で睨みつけた。
「越後屋、何を言いよる。わしは、弱き者を食い物にして、己の腹を満たしておるに過ぎぬ。そこを間違えるな」
「ははあ、滅相もございません! それがしの言い方が悪うございました。お代官様は、常に道理をもって悪事を働いておられると、申し上げたかったのでございます」
越後屋は慌てて訂正した。玄蕃は、不機嫌そうな顔で再び口を開いた。
「道理か…確かに、わしは銭のため、権力のためならば、いかなる悪事も辞さない。しかし、その過程には、常に計算と策略がある。計画もなく、ただ感情の赴くままに他者を害するなど、武士の道に反する」
玄蕃の言葉は、悪代官とは思えぬほど理路整然としていた。越後屋は、玄蕃の言葉に深く頷いた。
「お代官様の仰せの通りでございます。例えば、それがしが商売で人を欺く際も、そこには綿密な計画がございます。どのようにすれば相手を信用させ、いかにして銭を巻き上げるか。決して、感情に任せて取引をするようなことはございません」
「うむ、その通りだ。そこが、わしとそなたと、この『あおり運転』とやらを行う者との違いなのだろうな。わしらは、悪事によって何かを得ようとする。だが、奴らは、何も得ることなく、ただ感情の捌け口として他者を攻撃しておる。それでは、なんの益にもならぬではないか」
玄蕃は、まるで子供の喧嘩を評するような口調で言った。越後屋は、恐る恐る玄蕃の顔色を窺った。
「お代官様、では、その『あおり運転』とやらを行う者を、我々が悪代官の視点から見ると、どのように映るのでしょうか?」
玄蕃は、ふっと笑みを浮かべた。その笑みは、月の光に照らされて、より一層冷たく見えた。
「そうだな、越後屋。わしから見れば、彼らは愚か者だ。危険を顧みず、己の感情に振り回され、結果として罪に問われることもある。まるで、幼子が駄々をこねるかのようだ。悪事を働くのであれば、もっと賢く、もっと周到にやらねばならぬ」
越後屋は、玄蕃の言葉に戦慄した。玄蕃の悪事には、確かにどこか計算された美学があった。
「ははあ、お代官様のおっしゃる通りでございます。それに、お代官様は、常にリスクを考慮して行動なさいます。それがしも、お代官様のお手伝いをさせていただく際、常に万全の準備を怠りません」
「当然だ。いかに悪事とはいえ、失敗は許されぬ。計画を練り、裏工作を怠らず、万が一の事態にも備える。それが、悪事を成功させる秘訣よ」
玄蕃は、得意げに胸を張った。越後屋は、すかさず玄蕃を称賛した。
「まことにその通りでございます。お代官様の悪事には、常に学ぶべき点がございます。それに引き換え、その『あおり運転』とやらは、まったくもって…」
越後屋は、言葉を選びながら言った。玄蕃は、さらに言葉を続けた。
「それに、他者を威圧し、恐怖に陥れるという点では、わしの悪事と共通する部分もある。だが、わしは、そこから銭を巻き上げたり、己の権力を誇示したりする。彼らは、一体何を欲しているのだ?」
玄蕃は、まるで答えのない問いを自分に投げかけるかのように言った。
「お代官様、おそらくは…ただ、優越感に浸りたいだけなのではないでしょうか。あるいは、日頃のストレスを発散したいと」
越後屋は、自信なさげに答えた。玄蕃は、深くため息をついた。
「ふむ、くだらぬな。そんなもの、何の益にもならぬ。それならば、酒でも飲んで気分を晴らした方が、よほど健康的ではないか」
玄蕃は、呆れたように首を振った。越後屋は、玄蕃の言葉に同意しながらも、どこか寂しげな表情を浮かべた。
「お代官様のおっしゃる通りでございます。我々の悪事は、あくまで銭と権力のため。しかし、現代の世では、目的のない悪事が横行しているのかもしれません」
「目的のない悪事…か。それは、悪事と呼べるのか?」
玄蕃は、眉間に皺を寄せた。悪代官として、悪事には常に目的があるべきだと考えている玄蕃にとって、「目的のない悪事」という概念は、理解しがたいものだった。
「お代官様、それは…おそらく、悪事と申すべきか、愚行と申すべきか…」
越後屋は、言葉に詰まった。玄蕃は、ふっと笑みを浮かべた。
「いや、越後屋。それは悪事とは呼べぬ。ただの愚行だ。わしのような悪代官から見れば、彼らは甘っちょろい。悪事を働くならば、もっと覚悟が必要だ。もっと頭を使わねばならぬ。そうであろう?」
玄蕃は、越後屋に同意を求めた。越後屋は、深く頭を下げた。
「ははあ、お代官様のおっしゃる通りでございます。それがしも、お代官様のおそばで悪事を学ばせていただいている身。この『あおり運転』とやらを行う者たちの未熟さに、いささか呆れております」
「うむ。そうであろう。それにしても、現代の世も、なかなか面白いではないか。わしの生きていた時代には、考えられぬような悪事が横行しておるとはな。だが、やはり、根本は変わらぬな。人間の欲や、感情に振り回される愚かさ、そして、それを乗り越えられぬ弱さ。そうであろう、越後屋?」
玄蕃は、越後屋に問いかけた。越後屋は、玄蕃の問いに深く頷いた。
「ははあ、お代官様の仰せの通りでございます。人の世は、時代が移り変わろうとも、本質は変わらぬものなのでございましょう」
「うむ。そうであろう。さて、越後屋。今宵もまた、わしの腹を満たすために、一仕事頼むか」
玄蕃がにやりと笑うと、越後屋は待ってましたとばかりに頭を下げた。
「ははあ、喜んで。お代官様のためならば、いかなる悪事でも」
越後屋の言葉に、玄蕃は満足そうに頷いた。闇夜の中、二つの影は、再び街道を歩き始めた。現代の「あおり運転」を語り合った悪代官と越後屋の会話は、悪の哲学、人間の愚かさ、そして時代の移り変わりの中にも変わらない人間の本質を浮き彫りにした。悪代官から見ても「愚行」と評されるあおり運転は、現代社会が抱える病巣の一つなのかもしれない。
この物語は、悪代官と越後屋という独特の視点から、現代社会のあおり運転という問題を考察したものです。彼らの会話を通じて、あおり運転が単なる交通違反ではなく、人間の心の闇や社会のひずみを映し出す現象であることが示唆されています。