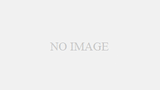「へっへっへ、越後屋、今日の儲けは上々じゃのう」
薄暗い座敷に響く、脂ぎった声。悪代官、黒沼玄蕃(くろぬまげんば)は、満足げに腹をさすりながら、向かいに座る越後屋宗右衛門(えちごやそうえもん)ににじり寄った。宗右衛門は、深々と頭を下げ、手元の帳簿を閉じる。
「ははぁ、これもひとえに、代官様のお導きあってこそ。おかげさまで、今月も順調に銭を稼がせていただいております」
「うむ、そちは口も達者じゃ。して、例の『袖の下』は、きちんと用意しておるであろうな?」
玄蕃がにやりと笑うと、宗右衛門は慌てて懐から小判の包みを取り出し、玄蕃の前にそっと置いた。ずしりと重い感触に、玄蕃の顔がさらに緩む。
「ぬし、相変わらず良いものを用意する。さて、本日はそなたに相談があるのだ」
玄蕃は小判を懐にしまいながら、急に真面目な顔つきになった。宗右衛門は訝しげに首を傾げる。
「と申しますと、一体…?」
「うむ。実はな、わしの孫が、近頃『お小遣いが少ない』と不平を申してきおる。現代の世では、子供の小遣いというものは、一体いくらくらいが妥当なものなのか、そなたの知恵を借りたいのだ」
宗右衛門は目を丸くした。まさか、悪代官から子供のお小遣いの相談を受けるとは夢にも思わなかったからだ。しかし、この機会を逃すわけにはいかない。宗右衛門は咳払いをして、すまし顔で話し始めた。
「なるほど。お子様のお小遣いですか。これはまた、奥深い問題でございますな。一口に『適正額』と申しましても、家庭の経済状況、お子様の年齢、お使い道の目的など、様々な要素が絡み合いますゆえ…」
「小難しい理屈はよい! 結論から申せ! ワシの孫は小学三年生じゃ!」
玄蕃が痺れを切らしたように言い放つと、宗右衛門は慌てて続けた。
「は、ははぁ。では、具体的な例を挙げてご説明させていただきます。まず、現代の日本では、**『年齢×100円』**という目安が一般的に言われております」
「ほう、年齢かける百円とな。すると、わしの孫であれば、三百円ということか」
玄蕃は顎に手を当てて考え込んだ。
「さようでございます。しかし、これはあくまで目安。例えば、お小遣いを定額制にするか、都度必要なものを与えるか、という点で議論が分かれます」
「定額制? 都度? また小難しいことを…」
「いえいえ、これはお子様のお金に対する考え方を育む上で、非常に重要な点でございます」
宗右衛門は得意げに続ける。
定額制と都度渡し、それぞれの利点と欠点
「まず、定額制でございますが、これは毎月、あるいは毎週、決まった額のお小遣いを与える方法です」
定額制の利点
- 計画性の養成: 決まった額の中でやりくりすることで、お子様は自然と計画的にお金を使うことを学びます。欲しいものがあった時に、すぐに買えるわけではないと知ることで、我慢することや、貯蓄することの重要性を理解するようになります。
- 金銭感覚の習得: 与えられたお金の範囲内で、何を買うか、何に使うかを自分で選択する経験を積むことで、物の価値やお金の重みを実感しやすくなります。
- 自己決定能力の向上: 自分のお金の使い方を自分で決めることで、自己決定能力が育まれます。これは、将来、大きな買い物や投資をする際にも役立つでしょう。
定額制の欠点
- 使いすぎの懸念: 計画性がないお子様の場合、すぐに使い切ってしまい、月末には一文無し、という事態に陥る可能性もございます。
- 不公平感の発生: 友達との間で、お小遣いの額が違うことで、不公平感を感じてしまうお子様もいるかもしれません。
- 親の管理の手間: 定期的に渡す手間がかかるほか、使い道について口出ししたくなる誘惑に駆られることもございます。
「次に、都度渡しでございますが、これはお子様が何か欲しいものを要求した際に、その都度、必要なお金を与える方法です」
都度渡しの利点
- 無駄遣いの防止: 必要なものにしかお金を与えないため、無駄遣いを防ぐことができます。
- 親の管理のしやすさ: 何にどれくらいお金を使ったかを把握しやすいため、親がコントロールしやすいという利点がございます。
- 急な出費への対応: 突然の出費にも柔軟に対応できます。
都度渡しの欠点
- 金銭感覚の欠如: 自分で計画的にお金を使う機会が少ないため、金銭感覚が育ちにくいという懸念がございます。お金は「言えばもらえるもの」という認識になってしまう可能性もございます。
- 自立心の妨げ: 自分で考えて行動する機会が少なくなるため、自立心が育ちにくい傾向がございます。
- 親子の衝突: 親が「これは無駄だ」と判断すると、お子様との間に意見の対立が生じ、衝突の原因となることもございます。
「むう、どちらも一長一短か。ワシとしては、いちいち金の管理をするのは面倒じゃから、定額制が良いと思うのだが…」
玄蕃は腕を組み、唸った。
「さようですね。しかし、定額制の場合でも、ただ渡すだけでは意味がございません。お子様としっかりと話し合い、お小遣いのルールを決めることが肝要でございます」
お小遣いのルールの重要性
「ほう、ルールとな?」
「はい。例えば、お小遣いの使い道について、ある程度の制約を設けるのです。例えば、お菓子代や文房具代はそこから出すが、友達との遊び代は親が出す、などです」
お小遣いのルール作りのポイント
- 透明性: 親子でお小遣いのルールを明確にし、共有することが大切です。何に使って良いのか、何に使ってはいけないのか、曖昧にしないことです。
- 目標設定: 貯金を促すために、「〇〇を買うために貯金する」といった目標を立てさせるのも良いでしょう。目標達成の喜びを経験させることで、貯蓄の習慣が身につきます。
- 家事手伝いと連動: お小遣いを、家事の手伝いと連動させるのも効果的です。例えば、「お手伝い〇回で〇円」といった具合です。これにより、労働の対価としてお金を得るという、社会の仕組みを学ぶことができます。ただし、お手伝いをしないとお小遣いがもらえない、という形にしてしまうと、お手伝いが義務になってしまうため、注意が必要です。あくまで、感謝の気持ちとして渡す、という姿勢が大切でございます。
- 失敗の経験: お小遣いを使いすぎてしまう、という失敗も、お子様にとっては貴重な経験でございます。すぐに助け舟を出すのではなく、一度失敗を経験させることで、次はどうすれば良いかを自分で考える力が育まれます。
「ふむ、なるほど。つまり、ただ銭を与えればよいというものではない、ということか」
玄蕃は真剣な顔で頷いた。
「左様でございます。お小遣いは、お子様が社会で生きていく上で必要な金銭感覚を身につけるための、大切な教育の機会でございます」
現代の子供たちの消費行動と教育
「ところで、越後屋よ。最近の子供たちは、一体何に銭を使うのじゃ? ワシらの時代とは違うのであろう?」
玄蕃の問いに、宗右衛門は待ってましたとばかりに口を開いた。
「ははぁ、鋭いご指摘でございます。現代のお子様方は、我々の時代とは比べ物にならないほど、多種多様な消費行動をしております」
現代の子供たちの主な出費項目
- お菓子・ジュース: これは昔も今も変わらぬ人気商品でございます。コンビニエンスストアやスーパーで手軽に買えるため、最も身近な出費と言えるでしょう。
- 文房具・雑貨: おしゃれな文房具や、キャラクターグッズなど、子供心をくすぐる商品が溢れております。友達との間で流行しているものも多く、ついつい欲しくなってしまうようです。
- ゲーム・アプリ課金: これが現代ならではの大きな特徴でございます。スマートフォンやゲーム機でのゲーム内課金や、新しいゲームソフトの購入などが、かなりの割合を占めております。
- 書籍・漫画: 学習漫画や流行の漫画など、子供たちの読書欲も旺盛でございます。
- レジャー・イベント: 友達と映画を見に行ったり、テーマパークに行ったり、といったレジャー費もございます。
- ガチャガチャ・くじ引き: 手軽に楽しめることもあり、つい何度も手を出してしまうお子様も少なくありません。
「むう、ゲームの課金とな…それはまた、厄介なものが出てきたものじゃのう。見えぬ銭が飛んでいくとは」
玄蕃は眉間にしわを寄せた。
「まさに仰る通りでございます。デジタルコンテンツは、形として残らないため、使った実感が薄く、歯止めが利きにくいという側面がございます。ゆえに、この点に関しては、親御様が特に注意を払う必要がございます」
金銭教育の重要性
「では、越後屋。結局のところ、わしの孫にいくら渡せばよいのだ?」
玄蕃が再び核心を突くと、宗右衛門はにこやかに答えた。
「ははぁ。結論から申し上げますと、小学三年生であれば、やはり月に1,000円から2,000円程度が妥当かと存じます。その中で、お菓子や文房具といった日常的なものをやりくりさせ、ゲームの課金など、高額なものについては、別途親御様と相談させる、という形が良いかと存じます」
お小遣いを通して教えるべきこと
- お金のありがたみ: お金は、誰かが働いて得たものであること、そして、そのお金を使って手に入れたものには、多くの人々の労働が関わっていることを教える。
- 感謝の気持ち: お小遣いを与えてもらっていることへの感謝、そして、そのお金で得たものへの感謝の気持ちを育む。
- 目標達成の喜び: 貯金をして目標を達成する喜びを経験させることで、将来の大きな目標達成にも繋がる。
- 社会とのつながり: お金を通じて社会がどのように回っているのか、経済の仕組みの基礎を教える。
「なるほど、月に千円から二千円か…案外少ないものじゃな。ワシはてっきり、もっとふんだんに与えるべきかと思っていたわ」
玄蕃は意外そうな顔をした。
「いえ、決して少なくはございません。肝心なのは、金額の多寡ではなく、そのお金をどう使わせるか、そして、そこから何を学ばせるかでございます。お子様が小さいうちから、お金の大切さ、使い方、そして、貯めることの重要性を教えていくことが、将来、自立した人間として生きていく上で、何よりも大切な財産となるでしょう」
宗右衛門は、心底からそう言い切った。玄蕃は、しばらく黙って考え込んだ後、ゆっくりと口を開いた。
「うむ…越後屋よ。そなたの申すことは、銭の亡者であるワシには、少々耳が痛い話であったが、まことに道理が通っておる。わが孫には、早速、そなたの教えを実践させてみよう」
玄蕃の言葉に、宗右衛門はにんまりと笑った。
「ははぁ! それはまことに結構なことでございます。そして、もし、お小遣いの管理で困ったことがございましたら、いつでも越後屋にご相談くださいませ。特別に、お子様向けの金銭教育プランなどもご用意させていただいておりますゆえ、へっへっへ…」
宗右衛門の言葉に、玄蕃はげんなりとした表情になった。どうやら、話の着地点は結局、越後屋の商売に繋がっていたらしい。
「こやつめ、ちゃっかりしおって。まあよい。今日のところは、そなたの知恵に免じて許してやるわ」
玄蕃は苦笑いしながら、再び懐を探った。
「では越後屋、この話の礼じゃ。これは内緒じゃぞ…」
宗右衛門の顔が、さらに満面の笑みになったのは言うまでもない。薄暗い座敷に、再び銭の匂いが満ちていくのだった。
「さて、代官様のお孫様は、このお小遣いをどうお使いになるのでしょうか。私も今から楽しみでございますな、へっへっへ…」
宗右衛門は、代官が去った座敷で、満足げに帳簿を眺めていた。