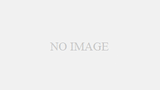梅雨明け間近の湿っぽい風が、黒沼玄蕃の屋敷の奥座敷に吹き込んだ。書見台に向かい、分厚い書物を読んでいた玄蕃は、顔をしかめて扇子をあおぐ。その隣では、茶菓子を前に越後屋宗右衛門がかしこまっていた。
「越後屋よ、今日のところはこれくらいで切り上げよう。どうにも蒸し暑くてかなわん」 玄蕃は書物を閉じ、ため息まじりに言った。越後屋は恐縮しきった様子で頭を下げる。 「はっ、お代官様におかれましては、さぞお疲れのことと存じます。つきましては、本日も例の品を……」 いつものように金の話を切り出そうとする越後屋に、玄蕃はぴしゃりと言い放った。 「待て、越後屋。今日は少々気分が乗らぬ。それより、そちに聞きたいことがあるのだ」 越後屋はきょとんとした顔で玄蕃を見つめる。悪代官の玄蕃が、金の無心以外で自分に話しかけるなど、よほどの事態である。 「お代官様、何なりとお申し付けくださいませ」 「うむ。実はな、最近耳にする『ひせいきこよう』とやらについて、そちの意見を聞きたいのだ。この玄蕃、どうにも腑に落ちぬことが多くてな」 玄蕃の言葉に、越後屋は一瞬眉をひそめた。現代の言葉である「非正規雇用」が、なぜこの悪代官の耳に届いたのか。しかし、玄蕃の好奇心を満たさねば、後々厄介なことになるのは目に見えている。 「はて、ひせいきこよう、でございますか……。恐縮ながら、それがしには少々耳慣れない言葉でして」 越後屋はとぼけたふりをするが、玄蕃はそれを許さない。 「とぼけるな、越後屋。そちほどの情報通が知らぬはずがあるまい。つい先日、この屋敷に出入りする若い者が、その『ひせいき』とやらで苦しんでいるとこぼしておったわ。それ以来、気になって仕方ないのだ」 玄蕃の鋭い眼光に、越後屋は額に冷や汗をかいた。この悪代官は、己の悪行には貪欲だが、意外と世情には敏感なところがある。特に、庶民の生活の匂いを嗅ぎつけることにかけては、鼻が利く。 「ははあ、なるほど。お代官様におかれましては、そのようなことまでお気になさるとは……恐悦至極にございます」 越後屋は内心舌打ちしながら、ゆっくりと話し始めた。 「その『非正規雇用』と申しますのは、現代において働く者の働き方の一種にございます。かつては、一つの仕事に就けば、死ぬまでその仕事に就くのが当たり前でございましたが、現代は少々事情が異なります」 「ふむ。つまり、定職に就かぬということか?」 玄蕃は腕を組み、越後屋の言葉を促した。 「はい。定職、と申しますか、『正規雇用』と呼ばれる働き方と対になるものでございまして、多くは契約期間が定められていたり、時給制であったり、福利厚生なども手薄な場合が多いと聞いております」 「契約期間があるとな? それでは、いつ職を失うか分からぬということではないか。不安定極まりない話だ」 玄蕃は眉間にしわを寄せた。悪代官とはいえ、領民の安定した生活は、己の基盤でもある。あまりに不安定な状況は、領民の不満を増幅させ、ひいては己の地位を揺るがしかねないことを本能的に理解していた。 「お代官様のおっしゃる通りでございます。しかし、企業側からすれば、人件費を抑え、景気の変動に応じて人員を調整できる利点があるそうでございます」 越後屋は、商人の立場から現代の企業の思惑を説明した。玄蕃は扇子を閉じ、膝を叩く。 「なるほど。つまり、企業は都合の良いように、人を使い捨てるということか。それは、いかにも現代らしい考え方よな。我らの時代にも、日雇いの者や、奉公の期間が定められた者はいたが、ここまで大規模に、そして巧妙に利用するとは……」 玄蕃は遠い目をして、かつての時代と現代を比較する。 「左様でございます。それに、非正規雇用の形態は多岐にわたり、パートタイマー、アルバイト、派遣社員、契約社員など、様々な呼び名がございます。それぞれに細かな違いはございますが、総じて正規雇用に比べて立場が弱いのが特徴かと存じます」 越後屋はさらに説明を加えた。玄蕃は興味深げに頷く。 「ほう、呼び名がこれほど多いとは。それだけ多くの者が、その『非正規』とやらで働いておるということか。世は乱れておるのう」 「はい。中には、正規雇用への入り口として非正規雇用を選ぶ者もいると聞きます。しかし、多くはそのまま非正規のままであったり、契約更新を打ち切られたりするケースも少なくないと……」 越後屋の言葉に、玄蕃の顔が曇った。 「つまり、正規への道は狭き門ということか。それは、まるで砂漠の中のオアシスを探すようなものよな。夢を見させておいて、結局は叶わぬ夢と知らしめる。悪辣なやり口だ」 玄蕃は、己の悪行すら霞むかのような現代のシステムの非道さに、どこか感心し、そして憤りを感じているようだった。 「それに、お代官様。非正規雇用の方々は、正規雇用の方々と比べて、教育訓練の機会が少なかったり、昇進の道が閉ざされていたりすることも多いと聞きます。賃金も低く抑えられ、生活が苦しい方も少なくないと……」 越後屋は、非正規雇用の労働者が直面する厳しい現実を淡々と語る。 「教育訓練の機会が少ないとな? それでは、その者の持つ才を伸ばすこともできぬではないか。それでは、まるで畑に蒔いた種を、水もやらずに放置するようなものだ。やがて枯れてしまうのは当然の理。その者の能力を最大限に引き出さぬとは、何とももったいない話だ」 玄蕃は、人材の有効活用という視点から、非正規雇用の問題点を指摘した。 「お代官様のおっしゃる通りでございます。さらに申し上げますと、非正規雇用であるがゆえに、病気になった際の保障が手薄であったり、年金や医療保険といった社会保障の面でも不利な立場に置かれることが多いと聞いております」 越後屋は、非正規雇用の社会保障の問題に言及した。 「何だと? 病に倒れても満足な手当てが受けられぬとな? それでは、人が人として生きる最低限の保障すら与えぬというのか。それは、もはや人でなしの所業ではないか!」 玄蕃は、さすがに声を荒げた。己の悪行は、あくまで己の私腹を肥やすためのものであり、領民の生命の危機を脅かすようなことは、決してしなかった。むしろ、領民の不満が爆発しない程度に、アメとムチを使い分けてきた自負がある。 「お代官様のおっしゃる通りにございます。そのため、非正規雇用の方々の中には、経済的な理由から結婚を諦めたり、子を持つことを躊躇したりする者も少なくないと聞きます。結果として、少子化の一因にもなっているとか」 越後屋は、非正規雇用が社会全体に及ぼす影響について語った。 「ほう、少子化にまで影響するか。それは由々しき事態よな。国の礎たる民が減っては、いずれ国そのものが立ち行かなくなるではないか。我らの時代にも、米の収穫が減れば、年貢が減り、ひいては幕府の財政が傾くゆえ、飢饉には細心の注意を払ったものだが……」 玄蕃は、現代の少子化問題を、自らの時代の飢饉になぞらえて憂いた。 「しかし、お代官様。なぜそのような働き方がこれほど蔓延しているのか、それがしにも腑に落ちぬ点が多々ございます。企業が利益を追求するのは当然のことと申しましても、あまりに度が過ぎるようにも思えまして」 越後屋は、商人の立場から企業の行動原理を理解しつつも、非正規雇用の現状には疑問を呈した。 「うむ。そちの言う通りだ、越後屋。利益の追求も結構だが、それでは社会全体が疲弊してしまっては、元も子もない。結局は、誰も得をしないのではないか」 玄蕃は腕を組み、深く考え込んだ。 「考えられるとすれば、企業は目先の利益に囚われすぎているのかもしれません。あるいは、グローバルな競争の中で、人件費の削減が絶対的な命題となっているのかもしれません。他国の企業が非正規雇用を積極的に活用しているとなれば、自国の企業も追随せざるを得ないといった側面もあるかと」 越後屋は、現代の経済状況における企業の立場を推測した。 「なるほど、国と国との競争か。それは我らの時代の藩同士の争いに似ておるな。隣の藩が新たな産業で潤えば、こちらの藩も何か手を打たねば、という焦りにも似た感情か」 玄蕃は、現代のグローバル競争を、封建時代の藩の競争に重ねて理解しようとした。 「左様でございます。あるいは、企業の側にも、非正規雇用への依存を強めることで、従業員の士気が低下し、結果として生産性が落ちるという皮肉な結果になることもあると聞きます」 越後屋は、非正規雇用が企業にもたらす負の側面にも言及した。 「それは、まさに『痩せ細った牛からは良い乳が出ぬ』という道理ではないか。目先の金に囚われすぎて、未来を失うとは、愚かしいことよな」 玄蕃は、現代社会の抱える矛盾に、悪代官ながらも深い洞察を示した。 「では、お代官様。この非正規雇用とやらを、どうすればよろしいとお考えでございますか? やはり、すべて正規雇用に戻すべきなのでございましょうか?」 越後屋は、玄蕃の考えを探るように問いかけた。 「うむ……一概には言えぬな。世の中は常に変化しておる。すべてを元に戻せば良いというものでもないだろう。しかし、これほどまでに不安定な働き方が蔓延すれば、社会の根幹が揺らぎかねん」 玄蕃は、容易には答えが出せない問題であると理解していた。 「例えば、非正規雇用の方々の賃金を上げることで、生活を安定させる。あるいは、正規雇用への転換を促すような制度を設ける。あるいは、社会保障の面で、正規雇用と非正規雇用の差をなくすなど、様々な手立てが考えられるのではございませんでしょうか」 越後屋は、これまでの情報を元に、いくつかの改善策を提示した。 「ほう。そちもなかなか冴えておるな、越後屋。賃金を上げ、社会保障を充実させるか……。それは、企業にとっては痛手であろうが、長い目で見れば、社会全体が豊かになり、ひいては企業の顧客も増えるということになろう。正規雇用への転換を促すというのも良い。能力のある者が、いつまでも不遇のままであっては、社会にとって大きな損失だ」 玄蕃は、越後屋の提案に頷いた。 「しかし、お代官様。そのような改革を行うには、誰かが音頭を取らねばなりません。国が主導するのか、あるいは企業が自発的に行うのか……」 越後屋は、実現の難しさを指摘した。 「うむ。そこが難しいところよな。皆が己の利益ばかりを追求すれば、この問題は解決せぬ。やはり、上に立つ者が、民の暮らしを憂い、長きにわたる繁栄を願う心を持たねば、世は良くならぬ」 玄蕃は、自らの悪行を棚に上げ、政治のあるべき姿を語った。越後屋は、思わず苦笑いを浮かべた。 「お代官様におかれましては、まこと民を思うお心が深く……」 「おべんちゃらはよい、越後屋。しかし、この『非正規雇用』とやら、我らが時代に生きておれば、さぞかし美味い汁が吸えたことだろうな」 玄蕃はにやりと笑った。その顔には、悪代官らしい欲望がちらりと見え隠れする。越後屋もまた、満面の笑みで玄蕃に媚びへつらった。 「お代官様におかれましては、きっと現代にお生まれになられましても、時の権力者に取り入り、この非正規雇用とやらを巧みに利用し、私腹を肥やされたことと存じます。それがしとて、お代官様の知恵をお借りすれば、さらに巨万の富を築けたことでしょう」 「ハッハッハッ! 越後屋よ、そちも悪よのう。しかし、やはり、真に良い世の中とは、民が安心して暮らせる世のこと。いくら金を稼いでも、人心が荒れていては、いずれは破綻する。この『非正規雇用』の問題は、まさにその縮図であろう」 玄蕃は、再び真顔に戻り、扇子を静かにあおぎ始めた。 「それにしても、この話を聞いておると、わしらがいかに恵まれた時代に生きていたかを思い知らされるわ。いくら悪事を働こうと、身分だけは保証されていたのだからな」 玄蕃は、悪代官としての己の立場と、現代の非正規雇用の不安定さを比較し、複雑な表情を浮かべた。越後屋もまた、深く頷いた。 「まことに。現代の世は、便利になったと申しますが、その裏では、多くの者が不安定な生活を強いられておる。それがしには、到底理解しがたい世にございます」 「うむ。世の中は、常に良くも悪くも変わっていくものよ。しかし、人の営みの根幹にある、安心して働き、子を育て、老いていくという願いは、いつの時代も変わらぬもの。この『非正規雇用』の問題は、その根幹を揺るがすものかもしれぬな」 玄蕃は、遠くの空を見つめ、静かに呟いた。その表情は、悪代官のそれではなく、まるで哲人のようでもあった。 「越後屋よ、今日の話はなかなか考えさせられたわ。そちも、たまには気の利いた話をするではないか」 玄蕃は越後屋を褒め、にやりと笑った。越後屋は恐縮しきって頭を下げた。 「もったいのうございます。お代官様のお心にかないましたようで、なによりでございます」 「うむ。さて、それではそろそろ本題に入るか。例の品とやらは、今日こそは良いものを用意しておるのだろうな、越後屋?」 玄蕃は、再び悪代官の顔に戻り、越後屋に視線を向けた。越後屋は、待ってましたとばかりに顔をほころばせた。 「へへっ、もちろんでございます、お代官様。今宵も、お代官様の胃袋を唸らせる逸品と、お気に召すこと間違いなしの『袖の下』をご用意させていただきました」 越後屋は、意味深な笑みを浮かべ、懐からきらびやかな小箱を取り出した。玄蕃もまた、満足げな笑みを浮かべた。 「うむ、そちはやはり、わしが一番信頼する商人よ。さあ、見せてもらうとしようか」
かくして、悪代官と越後屋の密談は、現代社会の抱える問題へと飛び火し、そしていつも通りの悪の取引へと戻っていくのであった。しかし、玄蕃の心には、非正規雇用の問題が、微かながらも影を落とし続けていたのかもしれない。現代社会の抱える闇は、悪代官の心をも揺るがすほどに深いものであった。