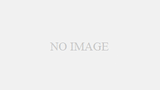現代の「お賽銭」談義:悪代官と越後屋の視点
梅雨明け間近の蒸し暑さが残る、とある夏の日の夕暮れ。江戸はずれの黒沼屋敷の一室では、障子を透かして射し込む夕日が、座敷の埃っぽい空気にきらめきを与えていた。
蚊遣り豚から細く立ち上る煙が、部屋の隅でじっと座す男たちの顔をぼんやりと霞ませる。一人はこの地の悪代官としてその名を轟かせ、領民から搾り取ることにかけては右に出る者とてない、黒沼玄蕃。
もう一人は、その玄蕃に取り入り、様々な不正を働くことで私腹を肥やすことに余念がない、御用商人・越後屋宗右衛門である。
重い沈黙を破ったのは、扇子でゆったりと顔を仰いでいた玄蕃であった。
「越後屋、近頃の世情は、誠に奇妙なものよな」
玄蕃の声は、普段の威圧的な響きとは異なり、どこか思案げな響きを帯びていた。宗右衛門は、すかさずお銚子を玄蕃の猪口に注ぎながら、愛想の良い笑みを浮かべる。
「は、玄蕃様。仰せの通りにございます。とりわけこの度、都で耳にした話は、まことに面白うございました」
宗右衛門の言葉に、玄蕃は小さく頷いた。
「うむ。私も耳にした。なんでも、賽銭というものが、世に広まっているとかなんとか」
「左様にございます! それが、ただの賽銭ではございませんで。近頃は銭だけでなく、硬貨なる金属の円盤や、はては札なる紙切れまで放り込むとか。しかも、神社仏閣だけでなく、何でも『イベント』とやらでも行われると聞きました」
宗右衛門は、まるで珍しい見世物を語るかのように、目を輝かせながら続けた。玄蕃は、興味深げに眉をひそめる。
「ほう、『イベント』とな? それはまた、いかなる催しであるか」
「それが、催し自体は様々でございまして。祭りから、歌や踊りを披露する場、はては、何やら得体の知れぬ『キャラクター』とやらが並び、それに銭を投げ入れるというようなものまであるとか」
宗右衛門は、首を傾げながら話す。玄蕃は、盃を口に運びながら、深く息を吐いた。
「ふむ。我らの時代にも、神仏への奉納金というものはあったが、まさか銭を投げ入れるなどとはな。しかも、それが『イベント』とやらにまで及ぶとは。世も末か、あるいは、新たな商機か…」
玄蕃の目は、既に悪代官のそれに戻っていた。宗右衛門は、玄蕃の意図を察し、にやりと笑う。
「さよう、玄蕃様。まさに、新たな商機と捉えるべきかと存じます。この越後屋、この賽銭なるもの、詳しく調べて参りました」
宗右衛門は懐から、墨痕鮮やかな巻物を取り出した。そこには、びっしりと細かい文字が書き込まれている。
「まず、この『お賽銭』という言葉の成り立ちでございますが、玄蕃様もご存じの通り、『賽』という字には、神仏に祈願成就の礼を述べる、あるいは誓いを立てるという意味がございます。つまり、元々は神仏への感謝の気持ちや、願いを込めて供える金銭のことでございますな」
玄蕃は頷きながら、巻物を覗き込む。
「うむ。それは理解できる。だが、銭を『投げる』という行為は、いささか乱暴ではないか? 我らの時代ならば、丁寧に供えるのが筋であろう」
「そこが、現代の面白いところでございまして。どうやら、手軽さ、簡便さが重んじられているようでございます。わざわざ供物を用意する手間を省き、小銭一枚で済ませられる手軽さが、広く受け入れられている要因の一つかと」
「手軽さ、か…」玄蕃は、顎を撫でながら思案する。「しかし、それだけではあるまい。神仏への信仰心が薄れている、ということもあろうな」
「ご明察にございます、玄蕃様! まさにその通り。元々は篤い信仰心に基づいていたものが、現代ではより形式的な、あるいは習慣的なものへと変容している嫌いがございます」
宗右衛門は、さらに巻物を広げた。
「現代においては、『小銭を放り込む』という行為自体が、一種の儀式めいたものになっているようでございます。特に若い者は、それが何であるか深く考えずとも、皆がやっているから自分もやる、という風潮が強いとか」
「なるほど、それは我らの時代の『おまじない』のようなものか。深く意味を考えずとも、皆がやっているから、自分もやれば何か良いことがある、とでもいうか」
玄蕃は、口元に薄い笑みを浮かべた。
「左様にございます。そして、この『お賽銭』には、様々な意味合いが付与されておるようでございます。例えば、『ご縁がありますように』と五円玉を好んで投げ入れる者が多いとか。これなど、語呂合わせでございますな」
「語呂合わせ、か。馬鹿馬鹿しい。銭にそのような効能があるはずもなかろうに」
玄蕃は鼻で笑った。しかし、その目は、既にこの「馬鹿馬鹿しい」行為から、いかにして利益を搾り取るかという算段を巡らせていた。
「いえいえ、玄蕃様。それが現代の面白いところでございまして。人々は、そうした『験担ぎ』を好む傾向がございます。そして、さらに驚くべきことに、この賽銭というものが、ある種の『娯楽』の要素を帯びてきているのでございます」
「娯楽とな?」
「はい。例えば、テレビと申しますか、世の人々が自宅で見る芝居のようなものがございますが、その中で登場人物が神社仏閣でお賽銭を投げ入れる場面などを見ると、自分もやってみたくなる、という者が増えているとか。また、最近では『ガチャガチャ』などという、銭を投入すると何かが出てくる玩具のようなものも流行っているようでございまして、それに近い感覚で賽銭を投げ入れる者もいると聞きます」
玄蕃は、大きく目を見開いた。
「銭を投げて、何かが出てくるか! それは面白い。つまり、賽銭箱なるものは、巨大な『ガチャガチャ』とでもいうことか」
「まさにその通りでございます、玄蕃様! そして、この『ガチャガチャ』には、何が出るか分からない、という期待感がございます。人々は、賽銭を投げ入れることで、漠然とした幸運や、良いことが起こるのではないか、という期待を抱くのでございます。たとえそれが、単なる気休めに過ぎなかったとしても」
宗右衛門は、得意げに胸を張った。玄蕃は、腕を組み、深く考え込む。
「なるほど。つまり、この賽銭なるものは、信仰心だけでなく、人々の漠然とした不安や期待、そして娯楽への欲求に付け込むことができる、とでもいうことか」
「その通りにございます、玄蕃様! そして、この現代の世では、人々はより簡便に、より手軽に、そしてより気軽に、そうした『幸運』を求めようとするのでございます。かつてのように、何日もかけて参拝し、身を清めるような真似は、もはや時代遅れでございましょう」
「ふむ。では、この賽銭箱なるもの、我らが利用する手立てはないものか…」
玄蕃の目は、ギラリと光った。宗右衛門は、待ってましたとばかりに、さらに巻物を広げる。
「そこが、この越後屋が熟考した点でございます。現代では、この賽銭、神社仏閣だけでなく、様々な場所で行われていると申しましたな」
「うむ」
「実は、この『イベント』というものにこそ、我らが付け入る隙があるかと存じます。例えば、我らが新たに『福の神イベント』とでも銘打ち、巨大な賽銭箱を設置する。そこに人々は、幸運を求めて銭を投げ入れる」
「なるほど。だが、それではただの物乞いではないか。それでは、我らが悪名をさらに轟かせるだけではないか」
玄蕃は、不満げに言った。宗右右衛門は、にやりと笑う。
「ご心配には及びません、玄蕃様。ここが肝要でございます。人々は、単に銭を投げ入れるだけでなく、何か『見返り』を求めるものでございます」
「見返りとな?」
「左様にございます。例えば、賽銭を投げ入れた者には、もれなく『ご利益のお札』と称する紙切れを渡すとか。もちろん、何の効能もない紙切れでございますが、人々は喜んで受け取るでしょう。あるいは、『開運おみくじ』と称し、銭を投入すれば、吉凶を占う紙が出てくる仕掛けを設ける。その裏には、我らが仕込んだ『大吉』を多く忍ばせておくのでございます」
玄蕃は、膝を叩いて感嘆の声を上げた。
「なるほど! それは面白い。人々は、大吉が出れば喜び、さらに銭を投じるであろう。そして、我らはその銭を、そのまま懐に入れることができる。悪代官の面目躍如というものよ!」
「お褒めにあずかり光栄にございます、玄蕃様。そして、さらに巧妙な手口がございます」
宗右衛門は、声を潜めて続けた。
「現代においては、『キャッシュレス』と申しまして、銭を持ち歩かぬ者も増えております。そこで、この『お賽銭』も、電子的な方法で行えるようにするのです。例えば、『電子賽銭箱』とでも称し、銭を投入せずとも、何やら『カード』とやらをかざすだけで、銭が支払われる仕組みを設ける」
玄蕃は、目を丸くして驚いた。
「何と! 銭を触らずして、銭を得るとは! それはまさに、夢のような話ではないか!」
「左様にございます、玄蕃様。そして、この電子的な賽銭であれば、誰がいくら投じたか、全て記録に残すことができる。つまり、我々は、人々の信仰心、あるいは欲に付け込んだ『顧客情報』まで手に入れることができるのでございます。そして、その情報をもとに、さらに新たな商売を仕掛けることも可能でございます」
宗右衛門の言葉に、玄蕃の顔には、悪巧みを企む者の特有の笑みが広がった。
「越後屋、お主はやはり、わしの右腕よ! この『電子賽銭箱』、まことに面白い。これで、世の銭を根こそぎ吸い上げてくれるわ!」
「お任せください、玄蕃様。この越後屋、この新たな『お賽銭ビジネス』、抜かりなく仕込んで参ります。まずは、手始めに、領内の寺社仏閣に、この『電子賽銭箱』を設置することから始めましょうか。もちろん、住職には相応の『謝礼』を渡して、口止めは万全に」
宗右衛門は、にやりと下卑た笑みを浮かべた。玄蕃は、満足げに盃を飲み干し、扇子を大きく広げた。
「ふむ、よいな。世の愚かな民が、自ら進んで銭を差し出す様を見るのは、この玄蕃、まことに愉快なことよ。越後屋、抜かりなく事を運べ。そして、さらなる儲けの策を、常に怠るでないぞ」
「ははっ! この越後屋、玄蕃様のご期待に沿えるよう、粉骨砕身いたす所存にございます!」
宗右衛門は、深々と頭を下げた。外は既に闇に包まれ、虫の音が響き渡る。悪代官と悪徳商人の間で交わされた、現代の「お賽銭」を巡る悪しき談義は、こうして夜遅くまで続いたのであった。この日、彼らの企みによって、さらに多くの民が、その財布を空にすることになろうとは、誰も知る由もなかった。