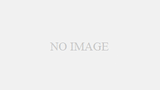「越後屋、今日の稼ぎはどうじゃった?」
黒沼玄蕃は、分厚い唇をにやりと歪め、越後屋宗右衛門に問いかけた。豪華な着物に身を包んだ宗右衛門は、深々と頭を下げ、座敷の奥に鎮座する玄蕃の前に座布団を引き寄せた。
「お代官様におかれましては、本日もご機嫌麗しゅう。おかげさまで、越後屋の商いは相変わらずでございます」
宗右衛門はそう言いながら、手際よく懐から取り出した扇子を開き、自らの顔を扇ぎ始めた。その顔には、金に塗れたような脂ぎった輝きが浮かんでいる。
「ふむ、それは結構。して、今日の面白い話は何かあるか? 世の中の移り変わり、特に金の話には目がないわしじゃて」
玄蕃は、喉を鳴らしながら茶を一口啜った。今日の茶は、越後屋が献上した最高級の宇治茶だ。
「ははあ。では、お代官様のお耳に入れとうございますのは、『お布施』についてでございます」
越後屋はにやりと笑い、玄蕃の顔色を窺った。玄蕃は興味深げに眉をひそめた。
「お布施とな? 寺に金を包む、あの古くからの慣習のことか。それがどうした?」
「それがでございますな、お代官様。最近の世は、お布施と申しましても、昔とは随分と様相が変わってまいりました。なにしろ、人が死なぬと金が落ちぬというのでは、商売としては少々寂しい」
越後屋はわざとらしく肩をすくめた。玄蕃は、その言葉の裏にある越後屋の思惑を即座に察知した。
「ほほう、面白いことを申す。では、越後屋、詳しく聞かせよ。その方、まさかお布施まで商売の種にしようと企んでおるわけではあるまいな?」
玄蕃は意地悪そうに目を細めた。越後屋は「まさか」と手を振りながらも、その顔には企みがはっきりと見て取れた。
「とんでもない。ただ、世の趨勢を鑑みれば、そこに新たな商機を見出すのは商人の性というものでございましょう。現に、葬儀の簡素化が進み、寺離れも囁かれる昨今。お布施の額も昔ほど期待できないと、坊主どもは嘆いております。その一方で、現代人は『心の平安』や『自己実現』といったものに金を惜しまない傾向がございます」
「ほう、心の平安とな。儂らが若い頃は、心の平安など銭があれば手に入るものだとばかり思っておったが、時代は変わるものじゃな」
玄蕃は顎を撫でながら、興味津々といった様子で越後屋の言葉に耳を傾けた。
「さよう。そこででございます、お代官様。現代のお布施は、もはや死者に捧げるだけでなく、生者の『心の贅沢』にこそ向けられているとわたくしは見ております」
「ほう、心の贅沢か。それはまた、妙な言い回しじゃな」
「例えばでございます。最近は、永代供養というものが流行っております。墓を持たずとも、寺が永代にわたって供養してくれるというもの。一見すると簡素化に見えますが、実はこれ、後顧の憂いを絶つという安心感を買う行為に他なりません。しかも、その寺が由緒正しい格式高い寺であればあるほど、その安心感は増し、お布施の額も跳ね上がるという寸法です」
「なるほど、安心感を銭で買うか。それは面白い。墓守りの手間を省きたい、子孫に迷惑をかけたくないという弱みに付け込むわけじゃな。越後屋、お主も悪よのう」
玄蕃はにやりと笑った。越後屋も負けじと笑みを浮かべた。
「お代官様ほどではございません。しかし、この永代供養、寺側もなかなか賢うございます。生前に契約を結ばせることで、確実に収入を得られますし、檀家が減る心配もございません。寺の存続にも寄与すると考えれば、まさにWin-Winの関係でございます」
「Win-Winとな、横文字を使うとは。しかし、その契約、一度金を払えばそれでお終いではないのか? 継続的な収入にはならぬではないか」
玄蕃が疑問を呈すると、越後屋はさらに奥の手があると言わんばかりに膝を叩いた。
「そこがでございます、お代官様! 寺はただ供養をするだけでなく、『心の寄りどころ』としての役割も担うようになっております。例えば、悩み相談、写経体験、座禅会、精進料理教室など、様々な催しを企画し、そこに参加料という形でお布施を募るのです。これらはあくまで『布施』という名目でございますから、納税の対象にはなりません」
越後屋は小声で付け加えた。玄蕃の目がキラリと光った。
「なるほど、それは美味い! 『お布施』という大義名分のもと、実質的な対価を徴収するというわけか。しかも非課税とは、抜け目ないのう。坊主どもも、なかなか世渡りが上手くなったものじゃ」
「さようでございます。しかも、それらの催しに参加する者たちは、単に知識や体験を求めているだけではございません。『心が洗われる』『癒やされる』『自分と向き合える』といった、精神的な充足感を求めております。そこに、お寺という『神聖な場所』が提供する付加価値が加わることで、参加者は喜んでお布施を支払うのです」
「ふむ、つまりは、**『体験』そのものがお布施の対象となり、その体験を通じて得られる『心の満足』**が、お布施の額を左右するというわけか」
玄蕃は腕を組み、深く頷いた。
「まさにその通りでございます、お代官様。そして、この『心の満足』をさらに高めるのが、**『特別感』**でございます。例えば、一般公開されていない秘仏の特別拝観、高僧による限定の法話会、あるいは、その寺にしかない特別な御朱印など。これらは、希少価値と特別感を演出することで、より多くのお布施を集めることができます」
「ほう、それは面白い。限定品や特別扱いには、人は金を惜しまぬものじゃからのう。わしとて、越後屋の特別仕入れの酒にはついつい財布の紐が緩むわい」
玄蕃はにやりと笑い、自らの経験に重ね合わせた。
「恐悦至極に存じます。そして、もう一つ、最近のお布施の傾向として顕著なのが、**『寄付型』**でございます。寺の修繕費や文化財の保護、あるいは地域貢献活動への支援など、具体的な目的を提示し、それに賛同する者から広く寄付を募るのです」
「それは昔からあったではないか。大仏建立の寄進など、例はいくらでもある」
「もちろんでございます。しかし、現代の『寄付型お布施』は、単なる金集めではございません。インターネットを通じて、寄付の使途を明確にし、進捗状況を公開することで、透明性と共感を呼ぶのです。寄付者は、自分が支払ったお布施がどのように活用されているかを知ることができ、社会貢献の一端を担っているという自己肯定感を得ることができます」
「なるほど、単なる施しではなく、まるで共同事業のような感覚か。寄付者も、自分が寺の一員になったような気分になるわけじゃな」
「さようでございます。さらに、最近ではクラウドファンディングを利用して、寺が資金を募るケースも増えております。これもまた、『お布施』の新たな形と言えましょう。少額からでも参加できるため、裾野が広がり、多くの人々から支援を得ることが可能でございます」
越後屋は得意げに胸を張った。
「クラウドファンディングとな、また横文字か。しかし、そうか、インターネットを使えば、全国津々浦々から金を集められるわけじゃな。わしも昔、この地の娘を都に売り飛ばすのに苦労したものだが、今なら簡単に人身売買もできるのかのう…」
玄蕃は遠い目をして呟いた。越後屋は愛想笑いを浮かべながら、話を元に戻した。
「お代官様、それは冗談としまして。要するに、現代のお布施は、もはや『死者のため』だけではなく、『生者のため』、ひいては**『自己のため』**へとその性質を変化させていると言えましょう。人は、自分の心を満たし、安心を得るためならば、金を惜しまない。寺は、その現代人のニーズを巧みに捉え、様々な形で『お布施』を集めているのです」
「うむ、誠にその通りじゃな。昔は、寺に金を施すのは、来世の安寧を願うためであったり、ご先祖様を供養するためであったりしたが、今は己の心の平穏のためか。世の中も変わったものじゃ」
玄蕃は感心したように頷いた。
「さらにでございます、お代官様。昨今、寺の中には、**『現代アート』と融合したり、『カフェ』を併設したりと、これまでの寺のイメージを刷新する動きもございます。これらは、若者層やこれまで寺と縁の薄かった人々を取り込むための工夫でございます。彼らにとって、寺はもはや敷居の高い場所ではなく、気軽に立ち寄れる『文化的スポット』**となる。そこで得られる体験が、結果としてお布施へと繋がるのです」
「カフェとな! 寺で茶を飲むとは、罰当たりな! いや、しかし、それは面白い。若者が寺に足を運ぶきっかけとなれば、いずれは檀家となるやもしれぬ。先を見据えた策と言えよう」
玄蕃は、その発想に驚きながらも、その巧妙さに舌を巻いた。
「さようでございます。寺側も、ただ古い慣習に囚われているだけでは生き残れないと悟っているのでしょう。時代に合わせて形を変える柔軟性が、現代のお布施を集める上では不可欠なのでございます」
「越後屋、その話を聞いておると、わしも寺の住職にでもなろうかと思うてしまうわい。金儲けの種はいくらでも転がっておるようじゃのう」
玄蕃は冗談めかして言った。越後屋はすかさず、
「お代官様は、悪代官としてこの国の金を掌握されるのが、何よりでございます」
と、お世辞を言った。玄蕃は満足そうに笑った。
「しかし越後屋、そうまでしてお布施を集めるとは、坊主どもも金の亡者よのう。昔は清貧を旨としておったはずだが、今や商売に長けた越後屋と変わらぬではないか」
玄蕃はニヤリと笑い、越後屋をちらりと見た。越後屋は扇子で口元を隠し、意味ありげな笑みを浮かべた。
「お代官様、それはお互い様というものでございましょう。清貧も度が過ぎれば、寺の維持もままなりません。寺もまた、世の中に存在し続けるためには、銭が必要でございます。そして、銭を集めるには、やはり世の趨勢を見極め、人々の心に寄り添うことが肝要でございます」
「ほう、坊主どもも、世の中の『欲望』を巧みに利用しておると言うわけか。欲深き人間から金を巻き上げる手腕は、わしとて見習うべきところが多々あるわい」
玄蕃は茶碗を置いて、深く頷いた。
「さようでございます。人々の『安心したい』『癒やされたい』『特別な体験をしたい』『社会の役に立ちたい』といった、様々な欲望が『お布施』という形で具現化されているのです。これらは、形を変えた**『心の渇望』と言えましょう。そして、寺は、その渇望を満たす『サービス』**を提供している、と」
越後屋は、まるで商売の極意を説くかのように語った。
「なるほど、サービスか。まさに、現代社会における寺は、**『心の総合デパート』**といったところか。ありとあらゆる心の悩みに対応し、それに見合ったお布施を徴収する。越後屋、お主の商売のやり方と、何ら変わりはないではないか」
玄蕃はそう言い放ち、越後屋の目をまっすぐに見た。越後屋は少しも動じることなく、涼しい顔で答えた。
「恐れ入ります。しかし、お代官様、そこにこそ、現代のお布施の本質があるとわたくしは愚考いたします。もはや、寺に金を納めるという行為は、信仰心だけに基づくものではない。むしろ、現代人の**『精神的消費』**の一環として捉えるべきでございましょう」
「精神的消費とな。消費税でもかけるべきか?」
玄蕃は冗談めかして言ったが、越後屋は真顔で首を振った。
「いえいえ、お代官様。それはご勘弁を。非課税であるからこそ、寺も喜んで様々なサービスを提供するのでございます。もし課税されるとなれば、途端にお布施の額も減り、寺の経営も立ち行かなくなりましょう。そうなれば、我々越後屋の商売にも少なからず影響が出てまいります」
越後屋は、寺の経営が傾けば、自身への献金も減ることを示唆した。玄蕃はそれを察し、大きく息を吐いた。
「たしかにそうじゃな。坊主どもが潤えば、わしらも潤う。持ちつ持たれつというわけじゃ。しかし、越後屋、その話を聞いておると、ますます思うわい。昔の坊主は、もっと質素で、世俗から離れておったものじゃがのう」
「時代でございます、お代官様。生き残るためには、変化せざるを得ません。寺もまた、世の中の荒波に揉まれ、時には悪知恵を働かせねばならぬ。そう考えれば、我々も坊主も、根は同じようなものでございましょう」
越後屋はそう言って、にやりと笑った。玄蕃もまた、その言葉に深く同意するように、大きく頷いた。
「たしかに、その通りじゃ。越後屋、お主の話はいつも面白い。今日の話も、大いに参考になったわい。さて、そろそろ、その方の用意した『お布施』を拝見するとしようか」
玄蕃は、そう言って手を差し出した。越後屋は満面の笑みを浮かべ、懐から分厚い包みを取り出し、深々と頭を下げて玄蕃に差し出した。
「お代官様、これはほんの心ばかりの『お布施』でございます。今後とも、越後屋の商売にご厚情を賜りますよう、伏してお願い申し上げます」
玄蕃は包みを受け取ると、その重みに満足そうに目を細めた。そして、再び喉を鳴らして笑った。
「うむ、越後屋。その方の『お布施』は、いつもわしの心を満たしてくれるわい。今日の話も、来世の安寧より、今世の安寧に繋がったようじゃのう」
二人の悪党の笑い声が、闇夜に吸い込まれていった。現代のお布施を巡る彼らの会話は、もはや信仰というよりは、したたかな世渡りの知恵と、人間の欲望を巡る考察であった。銭の匂いを嗅ぎ分ける彼らの鼻は、いつの時代も変わらない。