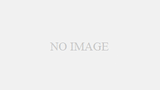夜のとばりが降りる江戸の町、黒沼玄蕃の屋敷では、いつものように密談が繰り広げられていた。対座するのは、悪事の片棒を担ぐ越後屋宗右衛門。今日の議題は、どうやら江戸を遠く離れた「現代」という時代の、奇妙な制度についてらしい。
「越後屋、そち、近頃巷で耳にする『国民健康保険』だの『社会保険』だのという話、一体どういうことだ?」
玄蕃は、分厚い眉をひそめ、いかにも不機嫌そうに問いかけた。手元には、どこからともなく手に入れたらしい、現代の制度を記したらしき奇妙な書物が広げられている。
「お代官様、それはまさに、わたくしめも頭を悩ませておりまする。何やら、人民から銭を巻き上げ、病に倒れた際にはその銭で治療を受けさせるという、まこと奇妙な仕組みでございます。」
越後屋は、にこやかに答えるが、その目にはいつものように打算の光が宿っていた。
国民健康保険:人民から巻き上げる新たな策?
「ほう、銭を巻き上げると申すか。それは聞き捨てならぬ。詳しく申してみよ、越後屋。」
玄蕃は身を乗り出した。銭という言葉に、悪代官の血が騒ぐ。
「ははあ。まず、『国民健康保険』と申すは、この国の全ての民が、いずれかの形で必ず加入せねばならぬものだとか。農民であろうと、町人であろうと、いや、お代官様のようなお役人様であろうと、皆が銭を出し合って、いざという時の備えとするのだそうでございます。」
「ふむ、つまりは、我々が年貢として米や銭を取り立てるのと、さほど変わらぬということか? 病にかからぬ者からも取り立てるとは、なかなか抜け目のない仕組みではないか。」
玄蕃は感心したように頷いた。越後屋は、すかさず言葉を継ぐ。
「お代官様の仰る通りでございます。しかも、この国民健康保険、その銭の額は、それぞれの稼ぎによって変わるとか。稼ぎの多い者からは多く、少ない者からは少なく、と。一見公平に見えますが、これはある意味、民の懐具合を筒抜けにするようなものでございますな。」
「なるほど、それは面白い。稼ぎを把握することで、より効率的に銭を吸い上げることができるというわけか。越後屋、そちならどうする? この国民健康保険とやらを、さらに我が物にする妙案はないか?」
玄蕃の目は、ギラリと光った。越後屋は、膝を叩いて得意げに語り始めた。
「お代官様、それは簡単でございます。まず、この『稼ぎによって額が変わる』という点。これを逆手に取るのです。例えば、稼ぎが少ないと偽る輩には、罰金を科すというのはいかがでしょう? そうすれば、皆、競って己の稼ぎを正直に申告するようになりましょう。いや、いっそのこと、病にかからぬ者にも、その分は『健康維持協力金』などと称して、余分に銭を納めさせるというのも一興かと。」
「くっくっく……越後屋、相変わらず悪知恵が働くのう。病にならぬ者にまで銭を要求するとは、さすがはそちじゃ。しかし、それでは人民が反発せぬか?」
「ご心配には及びません、お代官様。なにしろ、『万が一の備え』と申せば、人民は案外納得するものでございます。それに、病にかからなかった者には、後々何らかの形で『返還』するとでも言っておけば、より従順になりましょう。もちろん、その返還が滞るよう、巧妙に仕向けるのが、我々の腕の見せ所というもの。」
越後屋は、悪代官の前でさらにその本性を露わにする。
社会保険:企業と結託してさらに潤う道
「では、もう一つの『社会保険』とやらも詳しく聞かせよ。なにやら、大きな店や、役所で働く者たちが加入するものだと聞いたが。」
玄蕃は、次の書物へと目を移した。
「ははあ、お代官様。『社会保険』と申すは、従業員を抱える店や、お役所など、組織に属する者が加入するものでございます。これまた、毎月の給金から一定の銭が引かれ、雇用主もまた、同額の銭を負担するという、これまた不思議な仕組み。」
「なに!? 雇用主も負担だと? それはつまり、我々が越後屋を雇っておるように、越後屋もまた、己の店の者に銭を払うということか。そんなことをして、何の意味がある?」
玄蕃は、いぶかしげに首を傾げた。
「それが、お代官様、この社会保険には、『年金』という、老いて働けなくなった際に銭を受け取れる仕組みや、『介護保険』という、これもまた老いて介護が必要になった際に銭を受け取れる仕組みも含まれているのだとか。加えて、『失業保険』なるものまであり、職を失った者にも銭が支払われると申します。」
「ほう、それはまたずいぶんと手厚いではないか。しかし、それだけ多岐にわたる銭を、雇用主にも負担させるとなると、商売が立ち行かなくなるのではないか?」
「いえいえ、お代官様。そこがこの制度の巧妙なところでございます。雇用主は、この社会保険料を支払うことで、ある種の『福利厚生』として従業員の士気を高めると同時に、優秀な人材を確保できると考えるのだとか。それに、万が一の際には、国が面倒を見てくれるという安心感も得られる。つまり、表向きは従業員のためと見せかけつつ、実は雇用主もまた、この制度から利益を得ているわけでございます。」
越後屋は、にやりと笑った。
「なるほど、それは面白い。つまり、雇用主は銭を出す代わりに、従業員の忠誠心と、国による保障という『見えない恩恵』を得るというわけか。越後屋、この社会保険とやらを、さらに我々の儲けに繋げるにはどうすればよい?」
玄蕃は、再び目を輝かせた。
「お代官様、それは簡単でございます。この社会保険料、雇用主の負担分は、一種の『経費』として認められるそうでございます。つまり、支払った銭は、その店の利益から引かれ、税として国に納めるべき銭が減るというわけです。これを利用しない手はございません。」
「むむ、経費とな? それはまことに都合が良い。つまり、本来納めるべき税を減らしつつ、従業員には恩を着せられると?」
「左様でございます。我々は、この社会保険料を最大限に活用し、税を逃れるのです。例えば、従業員の給金を不必要に高く設定し、社会保険料の負担額を増やすことで、見かけ上は多額の社会保険料を支払っているように見せかけ、その分、利益を圧縮し、税を少なくする。いや、いっそのこと、存在しない従業員をでっち上げ、その分の社会保険料も計上することで、さらなる利益隠しを行うこともできましょう。」
越後屋は、悪びれる様子もなく、次々と悪だくみを口にした。玄蕃は、満足げに頷いた。
「くっくっく……越後屋、やはりそちはわしにとって、なくてはならぬ存在じゃ。この現代の奇妙な制度も、そちの手にかかれば、たちまち我らの銭蔵を潤す打ち出の小槌となる。それにしても、この現代の者たちは、なぜこれほどまでに、複雑で手間のかかる仕組みを作りたがるのかのう。我らのように、簡潔に年貢を取り立てる方が、よほど効率的だとは思わぬか?」
玄蕃は、ふと疑問を口にした。
「お代官様、それは恐らく、人民に不満を抱かせぬためかと。直接的に銭を奪うのではなく、『万が一の備え』だの、『互助の精神』だのと言葉巧みに説き伏せ、自ら進んで銭を差し出させる。まさに、現代の統治者が用いる、より巧妙な手口でございます。我々も、これからはそのような『大義名分』を掲げ、人民から銭を巻き上げる術を学ぶべきでございましょうな。」
越後屋は、深々と頭を下げた。その顔には、新たな悪だくみを思いついたかのような、にんまりとした笑みが浮かんでいた。
まとめ:時代を超えて変わらぬ悪の道理
「越後屋、今日の話はまことに有意義であった。国民健康保険と社会保険、一見複雑に見えるが、本質は我らが年貢を取り立てるのと変わらぬ。いや、むしろ、より巧妙に、より広く、人民から銭を吸い上げる仕組みであると理解したわ。」
玄蕃は、満足そうに腕を組み、ふと窓の外に目をやった。夜空には、煌々と月が輝いている。
「お代官様の仰る通りでございます。時代が移り変わろうとも、銭を求める者の心、そして、その銭をいかにして巻き上げるかという知恵は、決して廃れることはございません。むしろ、現代の制度を学ぶことで、我々はさらなる高みに到達できるかと存じまする。」
越後屋は、静かに答えた。
「うむ。明日からは、この現代の制度をさらに深く学び、新たな悪事を企てることとしよう。越後屋、そちの知恵、存分に貸してもらうぞ。」
「ははあ、お代官様。わたくしめ、身命を賭してお仕えいたしまする。」
二人の間には、深々と夜の闇が降りていた。しかし、その闇の中で、悪代官と越後屋の悪だくみは、さらに深く、そして狡猾に練られていくのであった。現代の「国民健康保険」と「社会保険」が、江戸の悪代官の目には、いかに映ったか。それは、時代を超えても変わることのない、人間の業と欲望の物語を雄弁に語っていた。
この国の「国民健康保険」や「社会保険」の制度、あなたは彼らの議論をどう感じましたか